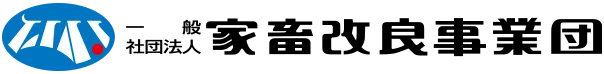2025年
令和7年度 和牛講演会を開催します
令和7年11月5日(水)、グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール(岡山県津山市)において、岡山種雄牛センター(場長 栗田 篤)主催による「令和7年度 和牛改良講演会」を開催いたします。
本講演会では、本年4月に公表された「肉用牛改良増殖目標」の検討委員会座長として策定に携わられた、独立行政法人 家畜改良センター十勝牧場 場長 河村 正 氏を講師にお迎えし、改良増殖目標のポイントについてご講演いただきます。
あわせて、同目標の中でも重要な位置付けとなっている「和牛ゲノミック評価」について、当団改良部部長 黒木 一仁より、その活用方法や今後の展望について講演いたします。
多くの皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
開催日時 令和7年 11 月 5 日(水)13:30~16:15 (13:00受付開始)
場所 グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール 岡山県津山市大田920
主催 (一社)家畜改良事業団 岡山種雄牛センター
演題 「新たな家畜改良増殖目標について」
講師 独立行政法人 家畜改良センター 十勝牧場 場長 河村 正 氏
演題 「今後のゲノミック評価について」
講師 (一社)家畜改良事業団 改良部 部長 黒木 一仁
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 岡山種雄牛センター 岡山県津山市宮部下415 担当 水野 賢一(みずの けんいち) TEL/FAX:0868-57-2475/0868-57-2476 E-mail:okayama_2006@liaj.or.jp |
令和7年度 和牛講演会を開催します
令和7年8月28日(木)に盛岡種雄牛センター(場長 桑原 孝博)主催の「令和7年度 和牛講演会」を姫神ホール(岩手県盛岡市)にて、開催いたします。
今年は、(株)茨畜連パイロットファーム鉾田牧場を運営され、原料と栄養価にこだわった配合飼料「名人」によって肥育された「名人和牛」の生産や、「名人会」という共励会を主催されている茨城県畜産農業協同組合連合会会長の中川徹氏をお迎えして、これからの和牛繁殖・肥育経営についてご講演いただきます。また、盛岡種雄牛センターからは、今期新たに選抜・供用する種雄牛についてご紹介させていただきます。
多くの方のご参加をお待ちしております。
開催日時 令和 7 年 8 月 28 日(木) 10:30~12:30
場所 姫神ホール 岩手県盛岡市渋民字鶴塚55
参加費 1,000円(テキスト代)
演題「これからの和牛繫殖・肥育経営について」
講師 茨城県畜産農業協同組合連合会 会長 中川 徹 氏
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 盛岡種雄牛センター 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5 担当 林田 光(はやしだ ひかる) TEL/FAX:019-683-2450/019-683-1334 E-mail:hi_hayashida_2006@liaj.or.jp |
2025年度乳⽤⽜改良推進実施計画の決定について
乳⽤⽜改良推進協議会(注1)は、ゲノミック評価を活かし、遺伝的能⼒等の情報発信を積極的に⾏いつつ、都道府県関係者と連携して、情報の活⽤促進と優れた国産種雄⽜の作出・利⽤拡⼤等に取り組み、我が国の乳⽤⽜改良を推進しています。
本協議会は、7⽉2⽇に開催した「 乳⽤⽜改良推進会議」(注2)を踏まえ、今後1年間の取組みをまとめた、以下を基本⽅針とする「2025 年度乳⽤⽜改良推進実施計画」を決定したのでお知らせします。
今回のポイントは、⽇本の飼養環境に即した疾病抵抗性の評価を8⽉から開始、2026-2 ⽉評価における疾病抵抗性を含んだNTPの改善です。
【2025 年度の基本⽅針】
乳⽤⽜の⽣涯⽣産性を⾼めるためには、泌乳能⼒とともに⻑命連産性に関わる耐久性や繁殖性、疾病抵抗性等の改良が課題である。⼀⽅、それらの形質は、飼養環境の影響を受けるため、⾼温多湿な⽇本の飼養環境に即した遺伝的能⼒評価の⾼度化・拡充が重要となっている。そのため、2023 年度に、参照集団の充実等により国内G評価の信頼性向上を図り、2024 年度にはNTP に、空胎⽇数と受胎率を含めた繁殖性指数と体のサイズを適正化するための⼤きさ指数を追加するなどの取組みを進めてきた。
2025 年度は、G評価のメリットをさらに活かし、⽇本の飼養環境への対応を加速化することを⽬指し、2つの柱・7項⽬を基本⽅針として取り組むこととする。
(1)⽇本の飼養環境に即した遺伝的能⼒評価の強化
① 疾病抵抗性の評価開始
6つの疾病(乳房炎、胎盤停滞、産褥熱、第四胃変位、乳熱、ケトーシス)の抵抗性及び疾病抵抗性指数のG評価を8⽉から開始する。
② NTPの逐次改善
2⽉評価において疾病抵抗性指数をNTPに追加するなど、NTPを逐次改善する。新たな国の改良⽬標を踏まえ、乳脂量と乳蛋⽩質量の割合⾒直しを検討する。
③ 肢蹄に関する指数の開発
蹄病に対する抵抗性や歩様等の遺伝的能⼒に基づく、肢蹄を強くするための指数の開発を進める。
④ 暑熱耐性の信頼度向上と評価形質の拡充
暑熱耐性の評価値について⽜群検定の乳中成分情報等の活⽤による信頼度向上の検討を進めるほか、新たな評価形質の開発を進める。
(2)⽇本の飼養環境に合った国産種雄⽜の活⽤拡⼤
⑤ 調整交配の改善
⽇本の飼養環境に合った種雄⽜選抜のため、G評価の信頼性維持・向上に必要な最新世代が ⼗分に確保できるよう、従来の仕組みを基本に調整交配の改善を検討する。(2025年度の調整交配頭数は2024年度を下回らない⽔準とする。)
⑥ 情報発信と連携を深めるための取り組み
よりわかりやすい、⾒やすく使いやすい情報の発信に努める。⾚本については、電⼦化の検討を進める。また、説明会や勉強会、意⾒交換の場などを充実する。
⑦ ヤングサイアの活⽤拡⼤
上記の取り組みを進めつつ、20%程度に⾼まってきたヤングサイアの活⽤をさらに拡⼤し、 国産種雄⽜による乳⽤⽜改良の加速化を図る。
◎実施計画全体はこちらをご参照ください
https://liaj.lin.gr.jp/wp-content/uploads/2025/07/202507_SUISHINKEIKAKU.pdf
(注1)乳⽤⽜改良推進協議会について
わが国の乳⽤⽜改良が多くの課題を抱える中、関係団体が同じ問題意識や⽅向性を持ち⼀体となって、課題解決に取り組むため、
(独)家畜改良センター
(⼀社)⽇本ホルスタイン登録協会
(⼀社)ジェネティクス北海道
(株)⼗勝勝家畜⼈⼯授精所
(⼀社)家畜改良事業団
が、令和2年11⽉に設⽴しました。本協議会は、各都道府県の乳⽤⽜改良関係者と連携して、我が国の乳⽤⽜改良を推進します。
(注2)乳⽤⽜改良推進会議について
乳⽤⽜改良推進会議とは、我が国の乳⽤⽜改良の⽅向性、後代検定や調整交配の全国調整、遺伝的能⼒評価の技術的⼿法など、それを実現していくための具体的な取組みを検討するため、酪農家や学識経験者、乳⽤⽜改良関係機関代表者等から構成される会議です。乳⽤⽜改良推進実施計画策定に当たっては、運営委員会や乳⽤⽜改良検討委員会(後代検定、遺伝評価技術)を設置し、技術的な検討を踏まえて決定しています。
| <お問い合わせ先> 乳用牛改良推進協議会 事務局 一般社団法人 家畜改良事業団 東京都江東区冬木11-17 担当 足達和徳(あだち かずのり)、大野 栞(おおの しおり) TEL/FAX:03-5621-8914/03-5621-8917 E-mail:adachi@liaj.or.jp |
令和7年度 和牛改良講演会を開催します
令和7年7月4日(金)、東海大学 阿蘇くまもと臨空キャンパス(熊本県益城町)にて、熊本種雄牛センター(場長:門脇 賢治)主催の「令和7年度 和牛改良講演会」を開催いたします。
今年度は、平準化事業の協力牧場であり検定済み種雄牛「福増秀(ふくますひで)」「伊勢之鶴(いせのつる)」を輩出した、株式会社三重加藤牧場 代表取締役社長 加藤 勝也 氏をお招きします。加藤牧場の循環型農業を取り入れた黒毛和種繁殖・肥育一貫経営での近江牛・松阪牛の生産、種雄牛作出の取り組みなどをご講演いただきます。
また、ゲノミック評価を活用した肉用牛産肉能力平準化促進事業の概要および、今期選抜されたR03現検前期新規種雄牛について、熊本種雄牛センター 業務課 主任 永井 慎太郎よりご紹介します。多くの方々のご参加をお待ちしております。
開催日時 令和7年7月4日(金) 13:30~16:30(開場13:00)
場所 東海大学阿蘇くまもと臨空キャンパス 2A203教室(2号館 A棟)
熊本県上益城郡益城町杉堂871-12
主催 (一社)家畜改良事業団 熊本種雄牛センター
演題「株式会社 三重加藤牧場の取り組み」(仮)
講師 (株)三重加藤牧場 代表取締役社長 加藤 勝也 氏
演題「平準化事業の概要及びR03現検前期新規種雄牛紹介」
講師 (一社)家畜改良事業団 熊本種雄牛センター 業務課 主任 永井慎太郎
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 熊本種雄牛センター 熊本県阿蘇郡西原村河原大野4332-16 担当 岡橋 勇太(おかはし ゆうた) TEL/FAX:096-279-2647/096-279-3496 |
令和6年度乳用牛群能力検定成績速報について
令和6年度乳用牛群能力検定成績速報をとりまとめましたので、その概要をお知らせします。
1.令和6年の305日乳量は、9,713kg(北海道9,709㎏、都府県9,721㎏)と令和5年を40㎏(北海道45㎏、都府県30㎏)下回り、2年連続の減少となりました (令和5年全国9,753㎏、北海道9,754㎏、都府県9,751㎏)。
※305日乳量は分娩してから305日間の泌乳記録を集計したものであり、本成績では、令和6年1月から12月に305日乳量が完成した記録になります。
2.繁殖成績は、分娩間隔が428日(北海道422日、都府県442日)と令和5年から3日(北海道3日、都府県2日)延びました(令和5年全国425日、北海道419日、都府県440日)。
3.令和6年度乳用牛群能力検定成績のまとめ(概況・速報)
URLhttps://liaj.lin.gr.jp/cowexam/gyuken_jitumu/gyuken_materials
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 情報分析センター 東京都江東区冬木11-17 イシマビル 担当 山口 茂樹(やまぐち しげき)、橋口 昌弘(はしぐち まさひろ) TEL/FAX:03-5621-8921/03-5621-8922 E-mail:toiawase@liaj.or.jp |
2024年
令和6年度 和牛改良講演会 沢山の方にご参加いただき終了しました!
令和6年10月30日(水)グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール(岡山県津山市)にて、一般社団法人家畜改良事業団 岡山種雄牛センター(場長 岩間 悟)主催の「令和6年度 和牛改良講演会」を開催しました。
中四国地方を中心に、各関係団体および生産者など約130名の方々に参加いただきました。
今回は、東京食肉市場株式会社 代表取締役専務 倉林 康樹 様を講師に迎え「東京食肉市場における枝肉動向の現状」~求められる枝肉に関する考察~ と題してご講演いただきました。
講演では東京食肉市場での生産地別の出荷頭数、枝肉規格等級別の取引状況などご説明いただきました。
また、飲食店、精肉販売店から求められる枝肉それぞれの特徴や、近年注目されている脂肪酸組成の取扱いについてなどの考察もいただきました。
参加者の方々には、和牛改良の一つの方向性としてお持ち帰りいただき、各県での和牛生産の参考にしていただければ幸いです。
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 岡山種雄牛センター 岡山県津山市宮部下415 担当 栗田 篤(くりた あつし)、水野 賢一(みずの けんいち) TEL:0868-57-2475 |
令和6年度 和牛改良講演会を開催します
令和6年10月30日(水)グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール(岡山県津山市)にて、岡山種雄牛センター(場長 岩間 悟)主催の「令和6年度 和牛改良講演会」を開催いたします。
今年度は、日本一の上場頭数を誇る東京食肉市場株式会社 代表取締役専務 倉林 康樹 様をお招きし、講演会直前10月25日に開催される全国肉用牛枝肉共励会の結果や枝肉の動向、昨今話題となっている脂肪の質などについてご講演いただきます。
多くの方のご参加をお待ちしております。
開催日時 令和6年 10 月 30 日(水)13:00~15:30 (12:00受付開始)
場所 グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール 岡山県津山市大田920
主催 (一社)家畜改良事業団 岡山種雄牛センター
演題 「東京食肉市場における枝肉動向の現状」
講師 東京食肉市場株式会社 代表取締役専務 倉林 康樹 様
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 岡山種雄牛センター 岡山県津山市宮部下415 担当 栗田 篤(くりた あつし)、水野 賢一(みずの けんいち) TEL/FAX:0868-57-2475/0868-57-2476 E-mail:okayama_2006@liaj.or.jp |
令和6年度 和牛講演会を開催します
令和6年8月29日(木)に盛岡種雄牛センター(場長 桑原 孝博)主催の「令和6年度 和牛講演会」を姫神ホール(岩手県盛岡市)にて、開催いたします。
今年は、令和5年度全国肉用牛枝肉共励会(東京食肉市場)において2連覇を達成され、令和5年8月に選抜した種雄牛 P黒1134 増平栄(父:福増)を生産された株式会社 松永牧場の取締役 松永 拓磨氏を講師にお迎えして、松永牧場グループの取り組みについてご講演いただきます。
また、盛岡種雄牛センターからは、今期新たに選抜・供用する種雄牛についてご紹介させていただきます。
多くの方のご参加をお待ちしております。
開催日時 令和 6 年 8 月 29 日(木) 10:30~12:30
場所 姫神ホール 岩手県盛岡市渋民字鶴塚55
参加費 1,000円(テキスト代)
演題「松永牧場グループの取り組みについて」
講師 (株)松永牧場 取締役 松永 拓磨 氏
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 盛岡種雄牛センター 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5 担当 林田 光(はやしだ ひかる)、吉澤 亜美(よしざわ あみ) TEL/FAX:019-683-2450/019-683-1334 E-mail:am_yoshizawa_2006@liaj.or.jp |
令和6 年度 和牛改良講演会を開催します
令和 6 年 9 月 4 日(水)グランメッセ熊本(熊本県益城町)にて、熊本種雄牛センター(場長:門脇 賢治)主催の「令和6年度 和牛改良講演会」を開催いたします。
今年度は、黒毛和牛の一大産地となった北海道において、近年和牛素牛市場で好成績を収めている「十勝和牛」の今に至るまでの取り組みについて、当団の北海道産肉能力検定場 場長 西部 博寿(元 十勝農業協同組合連合会 畜産部参与)より当団種雄牛とのかかわりを交えながらご紹介します。また、ゲノミック評価を活用した肉用牛産肉能力平準化促進事業の概要および、選抜されたR02現検後期新規種雄牛について当団の改良部 肉牛調査課 課長 四宮 将和よりご紹介します。
多くの方々のご参加をお待ちしております。
開催日時 令和 6 年 9 月 4 日(水) 13:30~16:30(開場13:00)
場所 グランメッセ熊本 熊本県上益城郡益城町大字福富1010
主催 (一社)家畜改良事業団 熊本種雄牛センター
演題「十勝和牛の歩み~家畜改良事業団 種雄牛との関わりあい~」
講師 (一社)家畜改良事業団 北海道産肉能力検定場 場長 西部 博寿(元 十勝農業協同組合連合会 畜産部参与)
演題「平準化事業の概要及びR02 現検後期新規種雄牛紹介」
講師 (一社)家畜改良事業団 改良部 肉牛調査課 課長 四宮将和
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 熊本種雄牛センター 熊本県阿蘇郡西原村河原大野4332-16 担当 岡橋 勇太(おかはし ゆうた)、沖津 和男(おきつ かずお) TEL/FAX:096-279-2647/096-279-3496 |
牛SNP型検査機関として国際認定を取得しました
(一社)家畜改良事業団(理事長 富田 育稔)の家畜改良技術研究所遺伝検査部は、牛のSNP型検査と親子判定を実施する機関の技術力を認定するICAR(家畜の能力検定に関する国際委員会)から、正確性を有した牛の「SNP型検査実施機関」として4月25日に認定を受けました。当団の本認証は、今回で6回目の更新となります。
ICAR は、家畜の識別、成績記録および評価に関するガイドラインの提供と技術力の認定を行なう国際機関であり、「SNP型検査実施機関」の認定を受けている検査機関は世界で16機関、うち日本においては唯一当団のみです。
当団は、乳用牛および肉用牛の改良等において、ゲノミック評価によって得られる情報の利活用が進む中、引き続き、その基礎となる正確なSNP型の提供に努めてまいります。
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 家畜改良技術研究所 群馬県前橋市金丸町316 担当 遺伝検査部 宮崎義之(みやざきよしゆき) TEL/FAX:027-269-2441/027-269-9331 E-mail:y-miyazaki@liaj.or.jp |
2024年度乳⽤⽜改良推進実施計画の決定について
乳⽤⽜改良推進協議会 (注1)は、各都道府県の関係者と連携して、国内ゲノミック評価の改善と普及に努め、優れた国産種雄⽜の作出とその利⽤拡⼤等に取り組み、我が国の乳⽤⽜改良を推進しています。
本協議会は、5⽉21⽇に開催した「 乳⽤⽜改良推進会議」(注2)を踏まえ、今後1年間の取組みをまとめた、以下を基本⽅針とする「2024 年度乳⽤⽜改良推進実施計画」を決定したのでお知らせします。
今回は、(1)のNTP の改善、(2)の疾病抵抗性等我が国の飼養環境に即した遺伝的能⼒評価の強化、(3)の搾乳ロボットへの適合性情報の提供がポイントです。
【2024年度の基本⽅針】
参照集団の充実等、2023年度の取組みにより、国内ゲノミック評価(以下「G評価」という。)の信頼性が向上した。
⼀⽅、ますます重要となっている乳⽤⽜の⽣涯⽣産性を⾼めるためには、泌乳能⼒とともに⻑命連産性の改良が課題である。⻑命連産性に関わる耐久性、繁殖性、疾病抵抗性等については、遺伝率が低く改良が難しい状況にあったが、G評価の信頼性向上により、効果的な改良が期待できるようになった。
2024年度は、そのようなG評価のメリットをさらに活かすことを中⼼に、次の7項⽬を基本⽅針として取り組むこととする。
(1)NTP の改善
耐久性、繁殖性、疾病抵抗性等が効果的に改良できるよう、NTP の改善を順次進める。
8⽉評価において、⼤きくなり過ぎた体の⼤きさを適正化する指数に加え、G評価により信頼度が向上した受胎率をNTP に追加する。併せて、表⽰⽅法について、遺伝率が低い形質の追加等に伴う数字の変化を抑え使いやすくするため、表⽰⽅法の⾒直しを⾏う。
(2)⽇本の飼養環境に即した遺伝的能⼒の評価
疾病抵抗性や暑熱耐性など、⽇本の飼養環境に合った能⼒が求められる形質の遺伝的能⼒評価の強化に取り組む。疾病抵抗性は準備ができ次第、遺伝的能⼒評価を開始しNTP に追加する。
(3)情報の拡充
搾乳ロボットへの適合性に関する情報の提供を8⽉評価から開始する。⼦⽜⽣存能⼒の遺伝的能⼒評価を2⽉評価から開始するとともに、歩様、妊娠期間などの新たな形質の検討を計画的に進める。
(4)後代検定の効率化とデータ収集の強化
調整交配を⾏うヤングサイアはさらに厳選する。その上で調整交配を最⼤限に活かし、国内G評価の信頼性の維持・向上のための最新世代のデータ収集の強化に務める。
(5)⾒やすさ、わかりやすさ、使いやすさに努⼒
遺伝的能⼒評価値をはじめとする情報が、より⾒やすく、わかりやく、使いやすくなるよう、提供⽅法の改善や説明ツールの充実に継続的に努める。特に、NTP の改善について⼗分な説明に努める。
(6)連携を深めるための取り組み
関係者の連携を深めるため、国内で乳⽤⽜改良を⾏う意義・⽬的、それを達成するための取り組みについて、わかりやすい資料の作成や情報発信等をこまめに⾏うとともに、説明会や意⾒交換の場などを設定する。
(7)ヤングサイアの活⽤拡⼤
上記の取組みを進めつつ、現状10%程度にとどまっているヤングサイアの活⽤を拡⼤し、国産種雄⽜による乳⽤⽜改良の加速化を図る。
◎実施計画全体はこちらをご参照ください
https://liaj.lin.gr.jp/wp-content/uploads/2024/05/202405_suisinkeikaku.pdf
(注1)乳⽤⽜改良推進協議会について
わが国の乳⽤⽜改良が多くの課題を抱える中、関係団体が同じ問題意識や⽅向性を持ち⼀体となって、課題解決に取り組むため、
(独)家畜改良センター
(⼀社)⽇本ホルスタイン登録協会
(⼀社)ジェネティクス北海道
(株)⼗勝勝家畜⼈⼯授精所
(⼀社)家畜改良事業団
が、令和2年11⽉に設⽴しました。本協議会は、各都道府県の乳⽤⽜改良関係者と連携して、我が国の乳⽤⽜改良を推進します。
(注2)乳⽤⽜改良推進会議について
乳⽤⽜改良推進会議とは、我が国の乳⽤⽜改良の⽅向性、後代検定や調整交配の全国調整、遺伝的能⼒評価の技術的⼿法など、それを実現していくための具体的な取組みを検討するため、酪農家や学識経験者、乳⽤⽜改良関係機関代表者等から構成される会議です。乳⽤⽜改良推進実施計画策定に当たっては、運営委員会や乳⽤⽜改良検討委員会(後代検定、遺伝評価技術)を設置し、技術的な検討を踏まえて決定しています。
| <お問い合わせ先> 乳用牛改良推進協議会 事務局 一般社団法人 家畜改良事業団 東京都江東区冬木11-17 担当 足達和徳(あだち かずのり)、大野 栞(おおの しおり) TEL/FAX:03-5621-8914/03-5621-8917 E-mail:adachi@liaj.or.jp |
令和5年度乳用牛群能力検定成績速報をとりまとめましたので、その概要をお知らせします。
1.令和5年の305日乳量は、9,753kg(北海道9,754 kg、都府県9,751 kg)と過去最も高かった令和4 年を186 kg(北海道208 kg、都府県139kg)下回りました。
(令和4年全国9,939 kg、 北海道9,962 kg、都府県9,890 kg)
2.繁殖成績は、分娩間隔が425 日(北海道419 日、都府県440 日)と令和4年から1日短縮(北海道2日短縮、都府県1日延長)しました。
(令和4年全国426日、北海道421日、都府県439日)
令和5年度乳用牛群能力検定成績のまとめ(概況・速報)
URL https://liaj.lin.gr.jp/cowexam/gyuken_jitumu/gyuken_materials
「乳牛最新情報」で検索
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 情報分析センター 東京都江東区冬木11-17 イシマビル 担当 山口 茂樹(やまぐち しげき)、橋口 昌弘(はしぐち まさひろ) TEL/FAX:03-5621-8921/03-5621-8922 E-mail:toiawase@liaj.or.jp |
「赤ペンコメント」を書き加えた牛群検定成績表の提供を開始しました
家畜改良事業団(理事長 富田 育稔)は、毎月の牛群検定の結果をとりまとめ提供している検定成績表に、着目すべき点を示し解説を加えた「赤ペンコメント」の提供を4月分から開始しました。(これまでに、全検定農家の4月分を提供しました。)
「赤ペンコメント」を書き加えた成績表は、牛群検定成績を早く使いやすく提供するためのWebシステムを通じて、以下のとおり提供します(郵送は行いません)。
飼養管理の改善や牛群改良をより効率的に進められるよう、検定農家の方々に加え、検定組合及び県指導機関の皆様にご活用いただければ幸いです。
【赤ペンコメントの概要】
・都府県の牛群検定農家に、乳量の変化に着目した「乳量編」と、体細胞数に着目した「体細胞数編」の2種類を提供します(別途費用は必要ありません)。
詳しくは、当団機関誌「LIAJニュ-ス」のNo.198およびNo.199をご覧ください。
URL https://x.gd/hoxN7(No198乳量編) https://x.gd/Zfdjf(No199体細胞数編)
・「繁殖台帳Webシステム」で閲覧できます。初めて利用する方等、利用方法が分からない場合は、検定組合にお尋ねください。
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 情報分析センター 東京都江東区冬木11-17 イシマビル 担当 相原光夫(あいはら みつお)(個体識別センター駐在) TEL/FAX:0248-48-0592/0248-48-0586 E-mail:toiawase@liaj.or.jp |
G-Eva®の利⽤申し込みが当団ホームページからできるようになりました!!
家畜改良事業団(理事長 富田 育稔)は、肉用牛ゲノミック評価Web 情報提供サービス(G-Eva®:ジーバ)について、新たに当団ホームページから利用申し込みができる機能を追加し、令和6年5月13日(月)より運用を開始しましたのでお知らせいたします。
今まで、G-Eva®の利用申込はゲノミック評価申込窓口団体を通じて受け付けていましたが、今回のバージョンアップによりゲノミック評価利用者が直接G-Eva®のログイン画面より申し込みができるようになりました。申し込み内容は当団とともに窓口団体にも通知され、より簡単にスピーディーに手続きができるようになりました。詳細は別紙または当団ホームページのG-Eva®利用方法をご覧ください。
<G-Eva®について>
G-Eva®は当団のゲノミック評価を実施した方が、スマートフォン、パソコン、タブレットから無料で利用できるサービスです。G-Eva®では、常に最新のゲノミック評価情報が確認でき、個々の牛あるいは牛群全体のゲノミック育種価の分析や選択した種雄牛との産子の能力予測も確認することができます。さらにDNA 情報に基づく遺伝的距離と産肉能力などのゲノミック育種価に基づいた交配種雄牛を自動で選定する機能も搭載しています。
ログイン画面:https://g-eva.liaj.jp/#/login
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 家畜改良技術研究所 群馬県前橋市金丸町316 担当 遺伝検査部 荻野 敦(おぎの あつし) TEL/FAX:027-269-2441/027-269-9331 E-mail:ogino@liaj.or.jp |
令和5年度のSNP検査の実施状況について
一般社団法人家畜改良事業団(理事長 富田 育稔)が令和5年度に実施した牛の SNP検査が76,663 件(乳用牛:31,003 件、肉用牛:45,660 頭)と過去最高の検査件数となりました。
SNP検査とは、ゲノミック評価(G評価)(注 1)等を行うために必要となるゲノム上に存在するおよそ5万か所の一塩基多型を検出するものです。
当団の家畜改良技術研究所(遺伝検査部)では、乳用牛の SNP 検査を平成 25 年度から、肉用牛のSNP検査を平成26年度から実施していますが、令和5年度はいずれも前年比30%以上の大きな伸びとなりました。
なお、乳用牛については当団が行った SNP検査に基づき(独)家畜改良センターがG評価を行い、申し込みから1カ月後にはその成績は(一社)ホルスタイン登録協会の GenIUS(注 2)で確認できるようになっています。
また、肉用牛については、当団で G評価を行い成績を提供しており、自身が所有する個体の情報はもちろんのこと、牛群の分析結果や個体の繁殖サポートとして、肉用牛ゲノミック評価 Web 情報提供サービス(G-Eva:無料)をご利用いただけます。
(注 1)従来の育種価評価に SNP情報を加えることで、若齢牛からでも信頼度の高い育種評価。全きょうだいの能力の違いも推定できる。
(注 2)乳用牛の牛群全体の能力を全国平均と合わせてグラフ上で見ることや、各個体の遺伝評価値を容易に確認できる情報提供システムです。
【遺伝検査部における検査技術能力について】
家畜改良技術研究所の遺伝検査部では、「牛SNP検査」について令和6年3月12日付けで国際規格 ISO/IEC 17025 の認定を取得しており、国際的にも信頼性の高い検査を実施しています。
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 家畜改良技術研究所 群馬県前橋市金丸町316 担当 遺伝検査部 塗本 雅信(ぬりもと まさのぶ) TEL/FAX:027-269-2441/027-269-9331 E-mail:nurimoto@liaj.or.jp |
牛のSNP検査について国際規格ISO/IEC 17025 の認定を取得しました
一般社団法人家畜改良事業団(理事長 富田育稔)の家畜改良技術研究所遺伝検査部は、令和6年3月12日付けで公益財団法人日本適合性認定協会(JAB:Japan AccreditationBoard)から、牛のSNP 検査についてISO/IEC 17025の認定を取得しました。牛のSNP検査における同規格の認定は国内初となります。
認定範囲は、イルミナ社と共同開発した独自のカスタムビーズチップであるXT チップを用いた毛根/耳片を材料とするSNP検査となっています。この認定は、当団のSNP 検査の信頼性の高さを示すものと考えておりますが、これを機に、さらに技術を高めるべく努力してまいる所存です。
(補足説明)
ISO/IEC 17025とは、特定の種類の試験・校正を実施する試験所・校正機関の技術能力を証明する国際規格です。技術能力には、職員の技術的力量、試験方法の妥当性・適切性、測定のトレーサビリティ、測定の不確かさの評価、試験機器・設備の適切性、校正・保守、試験品目の取り扱い・輸送、試験結果・データの品質保証等の要因が関係し、認定を受けるには、これらの要因に関する要求事項に適合する品質マネジメントシステムを構築・運用した上で、そのことを実証する必要があります。
| <お問い合わせ先> 一般社団法人 家畜改良事業団 家畜改良技術研究所 群馬県前橋市金丸町316 担当 遺伝検査部 塗本 雅信(ぬりもと まさのぶ) TEL/FAX:027-269-2441/027-269-9331 E-mail:nurimoto@liaj.or.jp |
リーフレット「ゲノミック評価と国産種雄牛が進化しました」の配布
及び動画「ゲノミック評価とヤングサイア」の公開について
乳用牛改良推進協議会は、都道府県団体等と連携して、我が国の乳用牛改良を推進するため、国内ゲノミック評価の改善と普及に努め、優れた国産種雄牛の作出とその利用拡大等に取り組んでいます。
本協議会は、今年度、ゲノミック評価の信頼度向上を図りつつ、ヤングサイアの活用拡大等に取り組んでいますが、今般、リーフレット「ゲノミック評価と国産種雄牛が進化しました」を作成するとともに、動画「ゲノミック評価とヤングサイア」を公開しました。
乳用牛の改良は、技術の進展に伴い難解さが増し、海外との競争も激しくなっています。我が国の酪農にとって必要な優れた国産種雄牛作出のための取組みには、酪農家をはじめとする関係者の皆様のご理解とご協力が不可欠です。今般のリーフレット及び動画が、ご理解を深めていただくための一助となれば幸いと考えています。
なお、リーフレットにつきましては、順次、牛群検定農家等に配布中であることを申し添えます。
リーフレットと動画、並びに本協議会の取組みについては、以下のページをご覧ください。
| <お問い合わせ先> 乳用牛改良推進協議会 事務局 一般社団法人 家畜改良事業団 東京都江東区冬木11-17 担当 足達和徳(あだち かずのり)、大野 栞(おおの しおり) TEL/FAX:03-5621-8914/03-5621-8917 E-mail:adachi@liaj.or.jp |